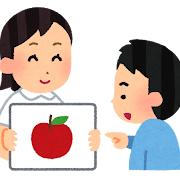みなさん、こんにちは。STkouhouです。
今日は、昨日に引き続き、吃音についてご紹介します!
吃音にはこころの支援も欠かせません。
言語聴覚学科には、臨床心理士の石本豪先生が所属しており、言語聴覚士の渡辺時生先生とともに吃音の方々へのお手伝いをしています。

言語聴覚士と臨床心理士の連携とは・・・?石本先生に聞いてみましょう。
Q1. 臨床心理士とはどのようなお仕事ですか
石本 臨床心理士は臨床心理学に基づく知識や技術を用いて、対象者を支援する心の専門家です。働いている領域は医療・保健、教育、福祉、産業・労働、司法・警察…など多岐に渡ります。それぞれの領域で多様な専門職と連携しながら仕事をすることも特徴のひとつです
Q2. 新潟医療福祉大学では吃音の患者さんに対して渡辺先生とどのような連携をしているのですか
石本 患者さんの吃音そのものに関しては言語聴覚士の渡辺先生が訓練や支援を担当してくださっています。私のほうでは、吃音から二次的に生じる心理・行動上の困り感が顕著な際に渡辺先生から患者さんをご紹介いただき、支援を行うことがあります。
心理・行動上の困り感としては、例えば、吃音があることによる気分の落ち込み…他者と会話することへの不安から対人関係に消極的になってしまう…などがあります。渡辺先生と情報交換をしながら、患者さんを多面的に理解し、支援できるような連携を心がけています。
Q3.吃音以外にはどのような支援をなさっていますか
石本 言語発達の遅れがあるお子さんをお持ちの保護者の方々を対象に対話を通じた支援を行っています。子供のことばの問題に伴い、保護者の方々も様々な心理的苦悩を体験しています。そのような苦悩を少しでも乗り越えられるようサポートできればと思っています。
本学の言語発達支援センターでは吃音だけでなく、様々なことばの問題を抱える子どもたちと保護者の方々への支援を行っています。
Q4. 臨床心理士と言語聴覚士の連携で大切なことはなんですか
石本 互いの専門性への関心と尊重でしょうか。言語聴覚士の先生方と接していると臨床心理士とは異なる技術や視点をもっていることに驚かされることが多々あります。
実際に支援をする際には、目的を共有することが大切だと考えています。何のために支援をするのか?ということです。そしてその目的を達成するためにはどのように連携したらよいかを考えることが重要だと思っています。
つまり連携すること自体が目的ではなく、連携は目的を達成するための有効な方法であるという考え方です。
Q5. 新潟医療福祉大学言語聴覚学科では、心理学をどのように学ぶのですか
石本 1年次から2年次にかけて「臨床心理学」や「発達心理学」など複数の心理学関連の科目が必修として開講されています。
授業の中で出てくるオペラント条件付け、レスポンデント条件付けといった概念は子どもの心理・行動上の問題に対する理解と支援におおいに役立ちます…ということを現在小児分野で言語聴覚士として働いている卒業生が、先日お会いした際に、私に気を遣いながら言ってくれていました(笑)。
また、3年次後期から配属される卒研ゼミでは、関心のある学生には言語発達支援センターでの臨床活動に関わってもらうことで、心理学を実践的に学ぶ機会を提供しています。

こちらは、相談に来られた方と石本先生がお話する際に使用しているお部屋です。

新潟医療福祉大学言語聴覚学科の特色の一つとして、言語聴覚士を目指しながら、石本ゼミに所属して心理学を専門とした卒業研究ができる!という点があります。
臨床心理士 石本先生の詳細はこちら→http://www.nuhw.ac.jp/faculty/medical/st/teacher/ishimoto.html
![]()